チームメイトにイライラ…どう扱えば、雰囲気も結果も良くなる?【根拠つき】
チームで長く過ごしていると、イライラは誰にでも起きる自然な感情です。ポイントは「抑え込む」でも「ぶつける」でもなく、うまく“扱う”こと。ここでは、感情を整えながらパフォーマンスと信頼関係を両立させる実践法を、医学・心理学の知見とともに解説します。

感情を「無かったこと」にすると、後で反動が来ます。言葉・呼吸・場づくりの3点セットで、冷静に共有できる土台を作りましょう。
まず押さえたい:イライラは“サイン”
- 価値観・役割・期待のズレを知らせる注意信号
- 放置すると集中低下・ミス増加・雰囲気悪化に波及
- うまく扱えば、改善点の共有 → チームの成長に変わる
根拠で選ぶ:実践4ステップ
① まずは体を落ち着かせる(60〜90秒)
ゆっくり息を吐く「スローブリージング」は、自律神経を整え、緊張・怒りの高ぶりを鎮めます。レビューや実験研究でも、ゆっくりした呼吸が情動調整に役立つことが示されています。 Boyadzhieva, 2021(総説, PMC) / You, 2021(実験, PMC)
- やり方:「4秒吸う → 6〜8秒かけて吐く」を1分。吐く時間を長めに。
- コツ:肩ではなくお腹が静かに動く程度でOK。
② 「今の気持ち」を短く言語化する(セルフ実況)
紙に一言で書き出す/小声でつぶやく——いわゆる感情のラベリングや筆記表現は、ストレス反応の軽減に役立つことが報告されています。受験生を対象とした筆記介入の無作為化試験では、心理的苦痛の改善が認められました( Marković et al., 2020, PubMed)。
- 書き方例:「今、○○の場面でイライラが8/10」「理由:役割のズレ」
- 数字(0〜10)で強さをつけると、客観視しやすくなります。
③ 攻めずに伝える:「Iメッセージ」+具体
相手を主語にせず、自分の気持ち → 影響 → 望む行動の順で短く伝えると、防衛的反応を減らせます。非暴力コミュニケーション(NVC)等のトレーニングでは、共感スキルの改善が確認されています( Rees et al., 2021, PubMed)。
④ 発散で終わらせない:「短い振り返り」を仕組みに
感情が爆発する前に、予定に組み込む“感情の棚卸しミーティング”が有効です。医療現場のパイロット研究ですが、短時間のクリニカル・デブリーフィングがチームの学習・連携に良い手応えを示しました。スポーツでも「短い振り返り」を定例化する意義は同様です( Kow et al., 2024, PMC)。
- 型(10分):①事実 → ②良かった1つ → ③改善1つ → ④次回の約束(担当・期限)
現場でそのまま使えるミニ台本(30秒)
- 呼吸2サイクル: 4秒吸う → 8秒吐く ×2
- 実況:「今、イライラ7/10。理由は連携ミス」
- 一言提案:「私、開始合図がないと焦る。次は『合図→パス』で合わせたい」
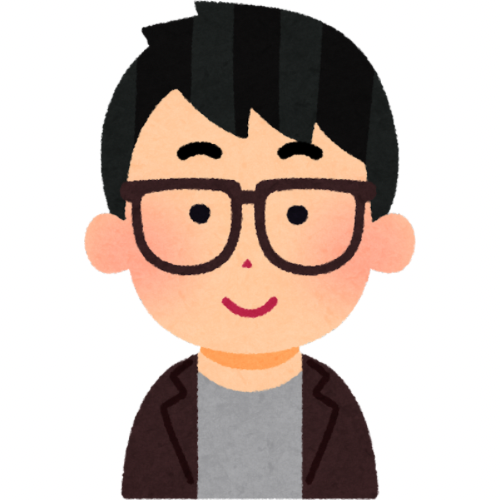
「週1・3行レポート」——(1)今週イライラした場面(事実)/(2)気持ち(0〜10)/(3)次の具体案(1つ)。3週分を見返すと、原因のパターン(役割・時間・言葉)が見えてきます。
さらに一歩:心理スキルは“チームの結果”にも効く
メンタル介入(呼吸・認知・コミュニケーションなど)を含む心理的トレーニングは、アスリートのパフォーマンス向上に効果があるとするメタ分析が報告されています( Reinebo et al., 2024, PubMed)。つまり、感情を整えるスキルは「気分のため」だけでなく、勝つための基礎体力でもあります。
参考文献(PubMed / PMC)
- Reinebo G, et al. Effects of Psychological Interventions to Enhance Athletic Performance. PubMed
- Boyadzhieva A, et al. Keeping the Breath in Mind: Respiration, Neural, Cognitive and Emotional Dynamics. PMC
- You M, et al. Slow-Paced Breathing Exercise. PMC
- Marković T, et al. Expressive writing intervention for test anxiety. PubMed
- Rees A, et al. Nonviolent Communication training improves empathy. PubMed
- Kow CS, et al. Clinical debriefs reinforce positive feedback climates. PMC





















コメント