【専門家対話コラム】ソマティック・エクスペリエンシング(SE)って何?
本コラムの軸は「身体の感覚を手がかりに、心の安全域を取り戻す」というSEの考え方です。ここに、実践手順・ケース例・よくある誤解・他療法との違いなどの枝葉を自然に重ね、誰でも今日から使える形に整理しました。


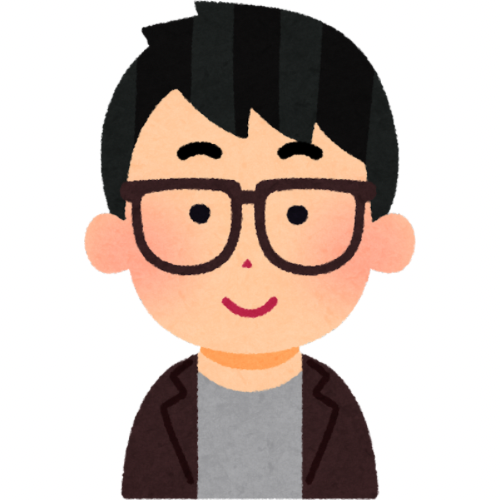
英語の原文イメージ(読み飛ばしOK)
“SE gently titrates sensations and pendulates between activation and settling,
helping the nervous system regain regulation without forcing verbal disclosure.”
英語は学習者向けの参考です。本文だけで理解できます。
SEが合いやすい人のサイン
- 出来事は過ぎたのに、体が先に固まる/息が浅くなる
- 人前・試合・試験などで過緊張になりやすい
- つらい体験を言葉にするのがしんどい(話すとぐったりする)
- 安心な場面でも、ふと体だけ警戒している感じが残る
ケースで理解:人前で声が震える高校生
本番前ルーティン(足裏→視線オリエンティング→5%ムーブ)で安定度UP。
よくある誤解と答え
- 「SEは何も話さない療法?」…いいえ。無理に語らないだけで、必要に応じて短く言葉を使います。
- 「早く深く向き合うほど効く?」…いいえ。SEは少量・短時間・往復が基本。急ぐほど反動が出やすいです。
- 「体の体操と同じ?」…違います。感覚の気づき(インターセプション)を育てる心理療法です。
他の療法との違い・併用の考え方
- EMDR:記憶の再処理に強み。SEで土台の安定→EMDRで記憶処理、という併用例が多い。
- CBT(認知行動療法):考え方・行動習慣を調整。SEは体感覚の安全を補強する土台に。
- 自律訓練法:自己リラックス訓練。SEの「気づき」と組み合わせると相乗効果。
オンラインで受けるときの準備チェック
- 座り慣れた椅子・足裏がしっかり着く環境
- カメラ位置は目線の高さ(呼吸・肩の動きが見えると良い)
- 「休憩合図」を事前に共有(例:手を胸に当てる)
- セッション後は水分・短い散歩・早めの就寝
用語ミニ辞典(英語は補助表示)
英語引用(学習者向け・任意)
“Titration approaches intense sensations in tiny doses.
Pendulation is the gentle movement between discomfort and comfort.”
よくある質問(FAQ)
Q1. つらい記憶を詳しく話さないと効果は出ませんか?
A. いいえ。SEは今の身体感覚に焦点を当てるため、無理に語らなくても進められます。
Q2. セッションの頻度と時間は?
A. 目安は50〜60分、2〜4週に1回。体調・目標により調整します(医療助言ではなく一般的な目安)。
Q3. セッション後にだるさや眠気が出ます。
A. 神経系が「緊張→ゆるみ」に動いたサイン。水分・散歩・睡眠で回復しやすくなります。
Q4. EMDRなど他の療法と併用できますか?
A. 併用例は多いです。SEで基礎の安定→EMDRなど記憶処理系へ、と段階を分ける選択もあります。
参考・背景情報
- Harwood-Gross ら(2025):PTSD文脈でSEを導入し、身体感覚への気づきと自己安定化の学習が進むことを報告。
- Payne・Levine・Crane-Godreau(2015, Frontiers in Psychology):内受容感覚(interoception)と固有感覚(proprioception)を核に据えたSEの理論的枠組みを概説。
※上記はSEの理解を助ける一般情報です。個別の診断・治療は、資格を持つ専門家にご相談ください。
まとめ
SEの本質は「身体から心を整える」こと。
劇的な変化を急がず、小さく触れて・小さく戻るの積み重ねが、やがて「安心の回路」を太くします。
まずは今日、足裏に戻る3呼吸から始めてみましょう。













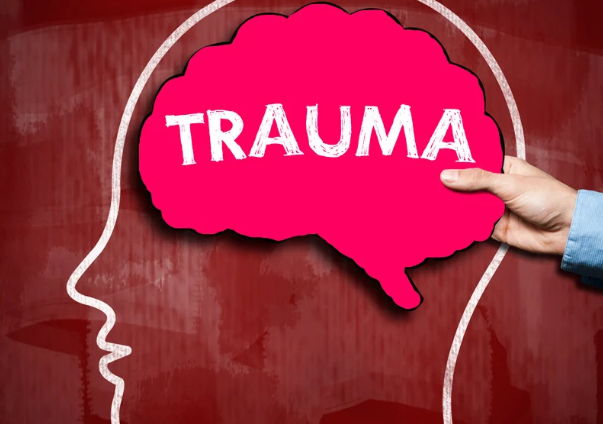







コメント