試合終盤、「あと少しで勝てそう」と思った瞬間に萎縮してしまう…どうすれば?

終盤で「もう少しで勝てる!」と思うと、逆に体がこわばって普段の動きができません…。頭では分かっているのに、結果を意識した瞬間にミスが出ます。

それはchoking under pressure(プレッシャーによる萎縮)と呼ばれる現象。結果を強く意識すると、熟練動作を“わざわざ考え直して”しまい(explicit monitoring)、自動化された動きが崩れます①。
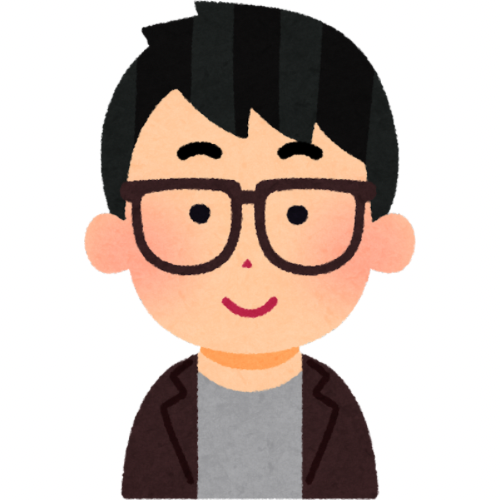
さらに、観客や視線・静まり返った会場などの社会的評価は緊張を高めやすく、成否に影響します。無観客試合でのデータからも“見られている感覚”が成績に響くことが示唆されています②。
「才能」ではなく心の状態のマネジメントで差が出る。終盤で結果に吸い寄せられた注意を、いま・ここ・この動作へ戻す設計がカギ。
科学に基づく対処:プレッシャーに強くなる3本柱
観客の前・点数掲示・罰ゲーム・時間制限など、意図的に緊張を上げた練習環境でリハーサルする。研究では、不安を伴う状況での練習が本番時のパフォーマンスを押し上げることが示されています③。
「入れる/勝つ」を考えるほど固まります。
終盤は合図語(キュー)で身体に戻すのがコツ:「膝→肘→フォロー」、「吸4・吐8」、「視線はボールの縫い目」など。マインドフルな注意配分は実行機能を保ち、集中の回復に有効です④。
プレッシャー下の対処法(再評価・前向きセルフトーク・プリパフォーマンス・ルーティン等)は、本番パフォーマンスの維持に効果があると総説で整理されています⑤。自分の型を短く・同じ順序で。
60秒で立て直す「終盤リセット・プロトコル」
- 姿勢を整える(5秒):背筋を立てて胸を開く。視線は水平。
- 呼吸で鎮静(20秒):「4秒吸う・8秒吐く」を2〜3回。吐く時間を長く。
- 合図語で“動作”に注意を戻す(10秒):例)「踏む→振る→止める」。
- ミスの扱いを固定化(10秒):「見る→言う→捨てる」。指先で軽く払う等のジェスチャー。
- ルーティンで再起動(15秒):同じ手順・同じテンポで入る。
責任の重さで潰れないために:認知の切り替え
- チーム戦:勝敗はプロセスの総和。「自分の一手はその一部」へ言い換える(責任の健全な分散)。
- 個人戦の気質が合う人:「すべて自分で引き受ける」と意味づけることで、自己効力感が上がり集中できるタイプもいる。大切なのは自分に合う意味づけを選ぶこと。
Q. 観客や視線が特に苦手。どう練習すれば?
小規模の公開練習、スマホ撮影、仲間に“わざと”静かに見てもらう等で社会的評価の再現を。始めは低プレッシャー→徐々に負荷を上げる段階設計に。
Q. 「勝てそう」の雑念が消えません…
雑念を消そうとせず、注意の置き換えで対応。「結果→体の感覚(接地・視線・呼吸)」へ戻す練習をルーティン化しましょう。
- 合図語(キュー)を3つ作る(例:踏む・見る・振る)。
- 同じ順序・同じテンポの15秒ルーティンを設計。
- 週2回の“緊張リハーサル”(観客役・制限時間・ご褒美/罰)を実施。
参考文献(PubMed/PMC への外部リンク)
- Beilock SL, Carr TH. On the fragility of skilled performance: What governs choking under pressure? J Exp Psychol Gen. 2001;130(4):701–725.(PubMed)
- van Besouw RM, et al. Who chokes on a penalty kick? Social environment and individual performance during COVID-19. Eur J Psychol. 2021.(PMC)
- (レビュー)プレッシャー下のトレーニングと介入の効果:O’Connor DB, et al. The effects of coping interventions on performance under pressure. Front Psychol. 2018.(PMC)
- Tang T, et al. Mindfulness improves cognitive control and academic performance: A meta-analysis. Front Psychol. 2023.(PMC)
ご相談はいつでも。匿名の質問でもOKです。状況に合わせて、練習設計やルーティン作りを伴走サポートします。


















コメント