大学生の「感情表現」とプレゼン不安――何が関係している?
3行で要点
- プレゼン不安はとても一般的。大学生の多くが人前で話す場面に強い不安を感じます。 [oai_citation:0‡スプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06216-w?utm_source=chatgpt.com) [oai_citation:1‡PMC](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12135526/?utm_source=chatgpt.com)
- 感情の出し方の違い(表に出す/内にためる)が、身体反応や対処の合う・合わないに影響します。 [oai_citation:2‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16938078/?utm_source=chatgpt.com)
- 自分の傾向に合わせた手順(話して整える/準備で整える)にすると、当日の安定感が上がります。 [oai_citation:3‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16938078/?utm_source=chatgpt.com)
読者からの質問

読者:
プレゼン前になると緊張で頭が真っ白に。これって性格の問題? それとも訓練で変えられますか?
ハタケの回答:性格より「仕組み」と「手順」

ハタケ:
人前での不安は珍しくありません。複数の調査でも大学生の多数がプレゼンを強い不安の場面として挙げています。大事なのは、自分の感情の出し方の傾向に合わせて対策を選ぶこと。これで「効く」方法が変わります。 [oai_citation:4‡スプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06216-w?utm_source=chatgpt.com) [oai_citation:5‡PMC](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12135526/?utm_source=chatgpt.com)
図解:感情の出し方と体の反応
- 表出型(気持ちを言葉や表情に出す)…不安を「話して」和らげやすい。
- 抑制型(気持ちを表に出しにくい)…外からは平静に見えても、心拍や筋緊張が上がりやすい。 [oai_citation:6‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16938078/?utm_source=chatgpt.com)
- 共通点…どちらの型も訓練で「戻る手順」を身につけると安定します(呼吸・最初の一文・視線の順)。
研究では、感情を抑え込むほど生理反応が強くなる傾向が報告されています。 [oai_citation:7‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16938078/?utm_source=chatgpt.com)
【対談】タイプの見立てと最新の測り方

ハタケ:
どうやって自分のタイプを把握すればいいですか?
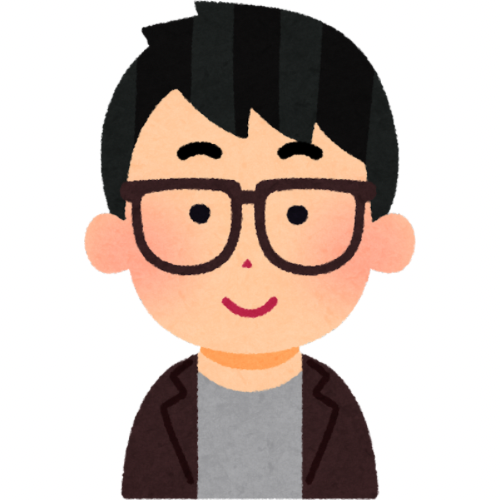
クロ先生:
質問紙が基本ですが、最近は表情や音声の変化を自動で拾う研究も進んでいます。学習場面でもAIの表情解析を使い、活動の様子を推定する試みが出てきました。自宅練習なら、スマホ録画を見返すだけでも自分の傾向が見つかります。 [oai_citation:8‡スプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1007/s40593-023-00378-7?utm_source=chatgpt.com) [oai_citation:9‡ACM Digital Library](https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696593.3696604?utm_source=chatgpt.com)

ハタケ:
では、型に合わせた「効く手順」を教えてください。
タイプ別|当日に効く3ステップ
表出型に効く
- ① 話して整える:本番前に友人へ「出だしだけ」声に出す→喉と表情がほぐれる。
- ② 1分ハミング:「んー」で口周りをゆるめ、最初の一文だけ低めに読む練習。
- ③ マイク前ルート:「吐く6秒→スライド左上を1秒→挨拶」を固定。“最初の10秒”を安定させる。
抑制型に効く
- ① 見出し3行カード:「挨拶/要点/着地」をカード化。飛んだら読むだけで復帰。
- ② 60秒の「吐く長め」:4秒吸う→6〜8秒吐く×5。抑制型で出がちな心拍上昇を静める。 [oai_citation:10‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16938078/?utm_source=chatgpt.com)
- ③ 小さな成功の先取り:1分録画→できた点を2つ書く。「自分はやれる」の予測を作る。
全員に効く|直前90秒ルーティン
- 呼吸:4秒吸う→6〜8秒吐く×5(肩を落とす)。
- 視線:資料の左上や会場の一点を1秒注視(視線を安定)。
- 声:ハミング10秒→最初の一文だけ低め&ゆっくりで読み出す。
※「緊張を消す」ではなく「高ぶっても戻れる状態」にするのが現実的です。
自分の傾向を知るミニチェック
- 不安は話すと軽くなる? → 表出型寄り。
- 不安は黙って準備すると軽くなる? → 抑制型寄り。
- どちらも当てはまる人はハイブリッド。両方の手順を持ち、場面で使い分けを。
まとめ:タイプに合う手順が、当日の安心をつくる
プレゼン不安は「珍しいこと」ではありません。自分の感情の出し方を知り、それに合った手順――話して整える/準備で整える――を用意すると、最初の10秒が安定します。今日の練習から、直前90秒ルーティンを組み込んでみましょう。
参考文献(クリック可)
- Lintner T., et al. Demographic predictors of public speaking anxiety among college students, 2024. Springer(米大学生のPSAに関する概観). [oai_citation:11‡スプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06216-w?utm_source=chatgpt.com)
- Ahmed WMM., et al. Public speaking anxiety and self-efficacy among medical students, 2025. Open Access. [oai_citation:12‡PMC](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12135526/?utm_source=chatgpt.com)
- Egloff B., et al. Anxiety, expression & suppression during public speaking, 2006. PubMed(抑制は生理反応↑の傾向). [oai_citation:13‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16938078/?utm_source=chatgpt.com)
- Gross JJ., John OP. Individual differences in reappraisal & suppression, 2003. PubMed(感情調整の個人差). [oai_citation:14‡PubMed](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12916575/?utm_source=chatgpt.com)
- Ngo D., et al. AI facial recognition in learning contexts, 2024. Springer(教育場面での表情解析の応用). [oai_citation:15‡スプリンガーリンク](https://link.springer.com/article/10.1007/s40593-023-00378-7?utm_source=chatgpt.com)
- Carvalho R., et al. Reliability of automatic facial emotion analysis tools, 2024. ACM. [oai_citation:16‡ACM Digital Library](https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696593.3696604?utm_source=chatgpt.com)
※本記事は一般情報です。強い苦痛が続くときは、大学の相談窓口や医療機関にご相談ください。






















コメント