催眠療法って怪しい?科学的エビデンスをチェック!
「操られそう」「寝かされるのでは?」というイメージとは異なり、催眠は
意識が保たれたまま、言葉・注意・イメージを使って
望ましい状態に切り替える心理的アプローチです。
ここでは、記憶・集中・パフォーマンスに関する研究で示唆されていることを簡潔に整理し、
今日から試せるミニワークも紹介します。
読者:催眠って、なんか怪しくて…「操られそう」で怖いです。
ハタケ:臨床での催眠は本人の同意と主体性が前提です。映画のような強制力は想定しません。
目的に合わせた言葉やイメージを使い、集中・リラックス・自己効力感などを整える支援に位置づけられます。
クロ先生:研究の質や結果には幅がありますが、行動療法やルーティンと組み合わせると、実行のしやすさを支える報告が複数あります。
研究から読み取れる3つのポイント
- ① 単独の“魔法”ではない:学習・反復・行動計画と併用して使う前提が現実的。
- ② 「実行のしやすさ」に寄与:緊張低下・注意の再集中・自己効力感の維持など、やるべき行動の後押しが示唆。
- ③ 個人差が大きい:効きやすい合図語やイメージは人により異なる。短く・肯定形・自分の言葉が鍵。
記憶・学習
一部の試験状況研究で、緊張の低下や集中の維持を通じて、学習内容の想起がしやすくなる示唆があります。
ただし効果の大きさは条件に左右されます。学習計画や睡眠衛生とセットで。
集中・パフォーマンス
スポーツ・発表場面などで、合図語+呼吸+イメージのルーティン化が、注意の再起動と自己効力感に寄与した報告があります。
身体スキル・症状
特定の運動課題や一部の機能性症状(例:局所性のこわばり等)で、行動療法と組合せて症状緩和や動作のスムーズさが示唆された事例報告があります。
本番前「60秒リセット」
- 姿勢セット:足裏フラット・骨盤を立て視線水平。
- 4-2-6呼吸 × 3回:鼻で4吸う→2止める→口で6吐く。
- 合図語を1回:「いま、ここ」(短く肯定形、自分の言葉)。
- 成功の最初の一手をイメージ:「最初の一文をゆっくり」など、最初の一動作だけ。
※体調に不安がある場合は無理をせず、中止してください。
催眠について知っておいてほしいこと
- 強制力はない:本人の同意や目的意識が前提。意識は保たれます。
- 医療の代替ではない:症状・病状がある場合はまず医療評価を。
- 万能ではない:学習・練習・睡眠・環境調整などの土台が重要。
文献を探すには(検索ヒント)
PubMed等で次を組み合わせて検索:
("hypnosis" OR "hypnotherapy") AND ("memory" OR "attention" OR "sports performance" OR "dystonia" OR "skill")













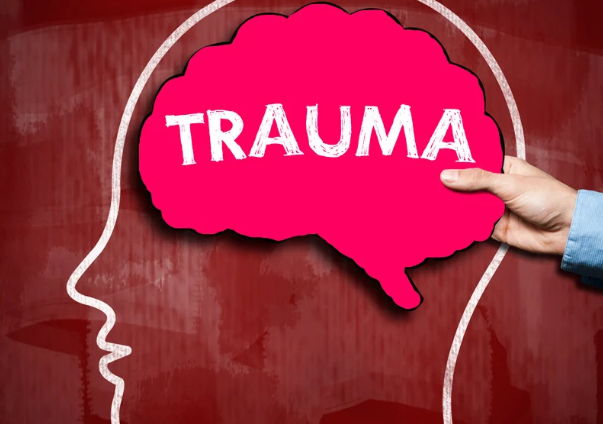







コメント